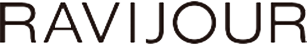#36 「22歳だったら」
SPECIAL COLUMN
#36 「22歳だったら」/妹尾ユウカ

「私が22歳だったら、本気で好きだったと思う」
これは早朝の中華料理屋で「そういえば彼は好みじゃないの?」とテキトーに尋ねてきた友人に対して、真剣に返した私の台詞。
彼を知る女からすれば、解像度抜群の一言であろう。近付くほどに湿っぽくて危うい。それなりの恋愛を経たアラサーが恋をしていいような相手ではない。きっと、人とお酒と酒の場が大好きで、いつも同じおいしくないタバコに違うライターで火を付ける人。押せば行けそうな隙があり、覗けば深そうな闇もある。37歳、独身貴族。
彼との出会いは、年始に行われた友人宅での新年会。都心のホームパーティーで出会う人間にしては口数が少なく、誰かの言うことによく笑ってはいたが、どこか暗い印象を持った。
経歴の華やかさに反して、密やかな気配りが抜群であることからも根明ではないことが伺えた。お酒がすすんで、ようやく彼はYouTuberや経営者、グラドルなどが集まるこの空間に馴染んでいったが、最初に抱いた印象が覆されることはなかった。
それから1週間後、私たちは新宿ゴールデン街で飲んでいた。ホームパーティーにいた友人と共に「ゴールデン街を案内してほしい」と彼にお願いをしたのがきっかけである。5年ほど前から、私もよく歌舞伎町内には出入りをしていたが、ゴールデン街に踏み入ったのはこの時が初めてだった。
わずか6500平方メートルほどの広さに、約280店舗もの飲食店がひしめいているらしい。「初級ならここですかね」そう言って案内されたお店の通路は"SASUKEファイナルステージ"を彷彿とさせる細さだった。
「気が合う」ってほどではなかったし、どちらかと言えば真逆の部類。学生時代、もしも同じクラスになったとしても話すことはなかったであろう人だったが、翌月も私は彼を誘って飲んでいた。
そんな関係が半年ほど続いたある朝、目が覚めると彼の腕の中にいた。一瞬、どこにいるのか分からないほど真っ暗な寝室だったが、部屋に漂うタバコの香りで、私の部屋ではないことが分かった。どうやってこの部屋まで辿り着いたのか、曖昧なくらいには飲んでいたが、これを「酒の勢いだった」と言うのはあまりに白々しいかもしれない。出会った頃からいつかこうなる予感はしていた。
それからも、ふたり、朝日から逃げるようにその寝室に飛び込んでは、大学生の夏休みのような体たらくな時を繰り返した。リビングに一歩出れば、嘘みたいな新宿が広がる窓の前で、さっきまでのことはなかったかのようにお互い敬語で言葉を交わす。関係が毎回リセットされる、何度会ったってよく知らない人。そんな距離感が好きだった。
彼とお酒の関係は、猫とまたたびのようなもので。その効果が発揮されているうちは、自分ことを話してくれた。学生の頃は、空か地面を見て過ごしていたこと、お父さんの正義感の話。そんな話の一つ一つは、まるでアドベントカレンダーをめくるような楽しさをくれた。あなたがあなたである理由はどれも全て素晴らしかった。
けれど、これ以上どうしたいという願望を私が持つことはなかった。ただ楽しさとして享受したい人、相手もそれを望んでいる人。うっすらずっと好きが心地いい。
可愛い私しか知らなくていいし、好きに暮らしているあなたがいい。理解するための話し合いとか、知った気になってガッカリするとか、あなたとはちっともやりたくない。
これは悲観しているわけでも、不貞腐れているわけでもない。出会った時から分かっていたことだが、彼とは絶対に合わないし、名称が付く関係になることもない。
そう分かっていても、この出会いは運命的なものであるはずと信じることができたり、そうなるように、相手に合うように、と自分を曲げられるのが22歳なんだと思う。
けれど、そんな風にして、どうにか隣にいられたところで、好きに振る舞う私を可愛いと思ってくれる人とじゃなきゃ、一緒にいたって自分が削がれていくだけだってことをもう知ってしまっている。27歳になってしまったから。
それでもきっと、これからもずっと、彼のことは少しだけ好きでいるのだと思う。
狂うほど好きにはなれないからこそ、終われることもなく、ずっと好きでいてしまうのだと思う。

妹尾ユウカ
独自の視点から綴られる恋愛観の毒舌ツイートが女性を中心に話題となり、
『AM』や『AERA.dot』など多くのウェブメディアや『週刊SPA!』『ViVi』などの雑誌で活躍する人気コラムニスト。
その他、脚本家、Abema TVなどにてコメンテーターとしても活動するインフルエンサー。